Excel 365 以降で利用できる DROP関数 は、表の先頭や末尾から指定した行数・列数をまとめて取り除き、必要な部分だけを切り出すときに便利な関数です。データの抽出や表の整形を効率化したいときに役立ちます。
DROP関数とは?
DROP関数 は、指定した範囲から「先頭もしくは末尾の行・列を削除した残り」を返す関数です。
主に次のような場面で使用します。
- 先頭の見出し行を除いたデータだけ抽出したい
- 不要な最終列を取り除きたい
- 表の一部を切り出して別の場所に展開したい
書式
=DROP(配列, 行数, [列数])
引数の説明
- 配列:対象となるセル範囲
- 行数:削除する行数(負の値を入れると「下から」削除)
- 列数(省略可):削除する列数(負の値で「右から」削除)
DROP関数の使い方
DROP関数では、指定した行数や列数を取り除いた“残りの範囲”をそのまま新しい配列として返します。
行数・列数を正の数にすると先頭から、負の数にすると末尾から除外できます。
例1:先頭1行を取り除く
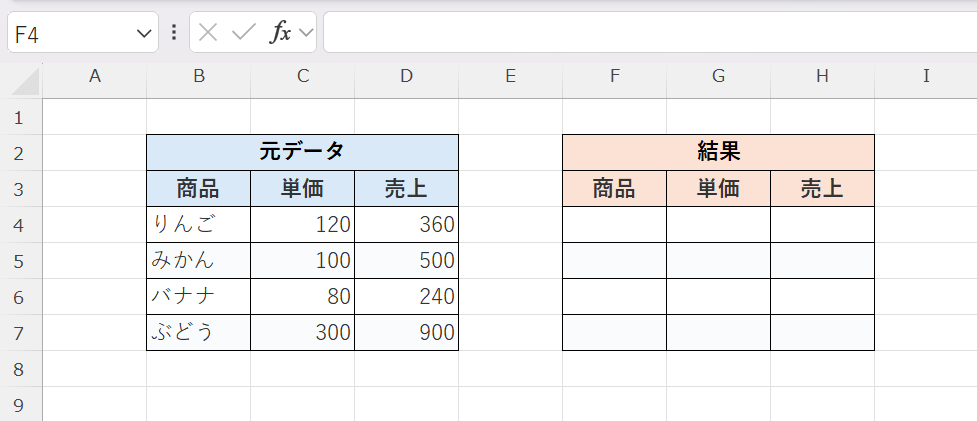
=DROP(B4:D7,1)
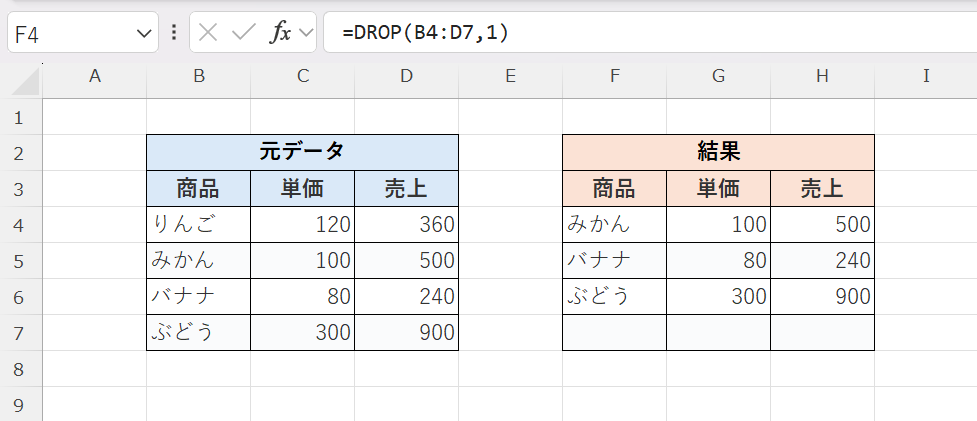
B4:D7 の範囲から 先頭1行 を除いた配列が返されます。
例2:末尾2列を取り除く
=DROP(B4:D7,0,-2)
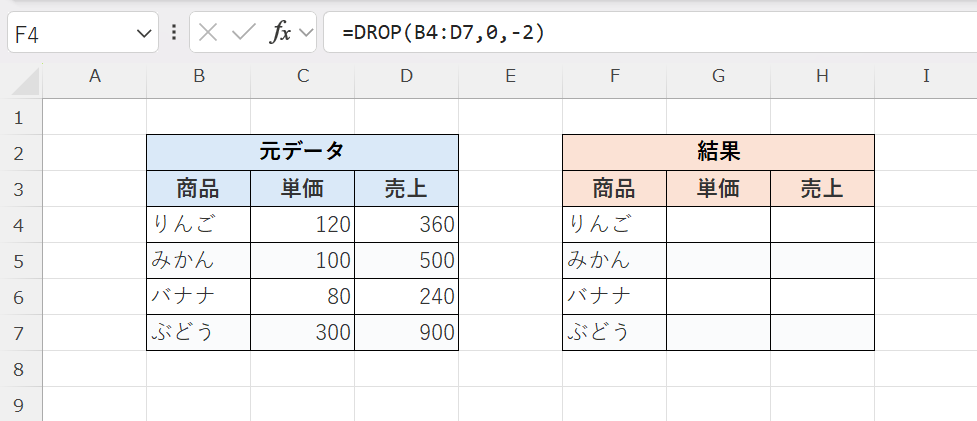
行の削除はせず、右側の2列 を削除した配列が返されます。
例3:先頭2行と先頭1列を取り除く
=DROP(B4:D7,2,1)
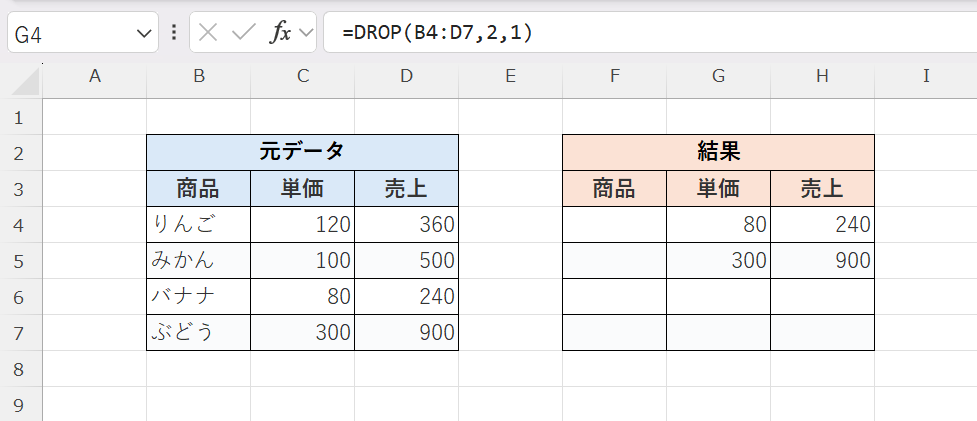
上2行・左1列を取り除いた残りの範囲が出力されます。
活用例
- データ分析前の前処理に
不要な見出し行や補助列をサッと取り除ける - 表の一部だけを別シートに展開
DROPで切り出し → そのままFILTER関数やSORT関数に連携 - 可変範囲の処理に強い
スピル動作により、行数や列数が変わっても自動で再展開される
注意点
- 利用には Microsoft 365(Excel 2021 以降) が必要
- 行数・列数に0を入力すると「削除なし」
- 返される結果はスピル範囲になるため、隣接セルにデータがあるとエラーになる
- 行数や列数が元の範囲を超えると #VALUE! エラー
関連関数
| TAKE関数 | 指定した行・列だけを抽出 |
| CHOOSECOLS関数 / CHOOSEROWS関数 | 特定の行・列を選択 |
| INDEX関数 | 範囲から任意のセルや行列を取り出す |
| FILTER関数 | 条件に一致する行を抽出 |
まとめ
DROP関数は、表の不要な部分を簡単に取り除ける便利な関数です。
行・列の削除を柔軟に設定でき、スピルによって自動で結果が更新されるため、表の前処理や抽出作業が大幅に効率化します。Excel 365 を使っているなら、ぜひ活用したい関数のひとつです。
